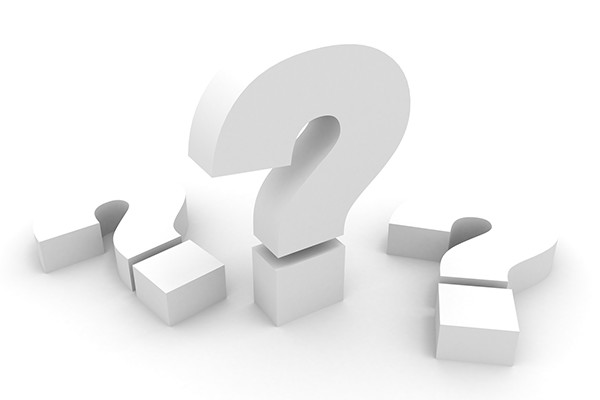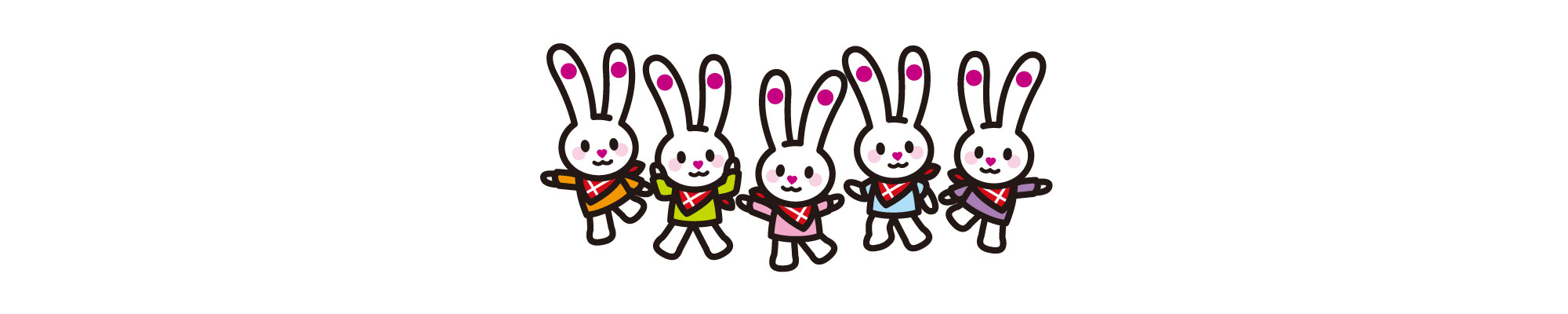近年、難聴と認知症の関連性は注目されており、難聴は認知症の予防可能な12の要因の中で最大の危険因子であることが明らかになっています。そこで難聴と認知症の関係性や対処法、予防方法について解説します。
難聴は認知症の最も大きな危険因子
2017年7月、国際アルツハイマー病会議(AAIC)においてランセット国際委員会が、難聴を認知症の危険因子として挙げました。特に認知症は「予防可能な40%の12の要因の中で、難聴は認知症の最も大きな危険因子である」とされています。
難聴による認知症発症リスクを示した研究によると、軽度難聴の方は正常な方と比較して、認知症発症リスクが2倍になっています。また中等度難聴の方は3倍、高度難聴の方の場合は5倍の発症リスクがあることがわかりました。
このように難聴と認知症には因果関係があるのです。
なぜ難聴になると認知症になりやすい?
私たち人間は、耳から得られた音を脳に送り、情報として処理しています。
誰かと会話する際は、耳から得られた音を言葉として認識し、コミュニケーションを取ります。音楽を聴く際は、空気の振動をメロディとして認識し「良い曲だな」などと心地よさを感じているのです。
このように人間の耳と脳は、起きているときだけでなく、寝ているときにも休まず機能し続けます。一方で難聴になると、耳から脳に送られる情報が大幅に減少します。
音の情報が入らなくなることで、前頭葉や側頭葉などの部位が影響を受け、認知機能の低下が起こるのです。
また難聴になると、他人の言っていることが聞き取りにくくなり、会話が成立しづらくなります。そのため、周囲とのコミュニケーションを避けるようになり、認知症のリスクが高まる可能性があります。
認知症を予防するために生活習慣を整えよう
難聴を放置すると、症状が進行し、認知機能が低下します。また最悪の場合、うつ病などの症状が発症するかもしれません。このような事態を防ぐためにも、生活習慣を整えることが大切です。
難聴の要因の1つとして挙げられるのが血液循環の悪化です。
喫煙の習慣や糖尿病などの生活習慣病を持つ方などは難聴のリスクが高まるとされています。そこでおすすめなのが、生活の中に運動習慣を取り入れることです。

週に1〜2回程度、散歩をしてみましょう。
散歩を習慣にすると、血液循環が良くなり、生活習慣病や難聴を止しやすくなります。
なるべく運動習慣を取り入れ、健康に配慮した生活を送りましょう。
聞こえに不安がある方は耳鼻咽喉科を受診しよう
ご自身で聞こえが悪くなったり、難聴かもしれないと感じたりすることはないでしょうか。もし、このような違和感がある方は、耳鼻咽喉科を受診することをおすすめします。
耳鼻咽喉科では聴力検査が可能です。
聴力検査では、難聴の有無、難聴がある場合その程度について確認できます。また難聴の種類まで明確にできるため、医学的処置、あるいは補聴器の使用が適切なのかを医師が判断することになります。
定期的に聴力検査することで、耳の状態や聞こえについて自身で把握できます。聴力検査を習慣づけることで、聴力に変化があった場合、すぐに把握しやすくなります。難聴は放置すると、症状がどんどん悪化するため、早期発見・早期治療することが重要です。
聞こえに関して少しでも異変を感じたら、速やかに耳鼻咽喉科を受診しましょう。
まとめ
難聴は認知症の最も大きな危険因子とされています。認知症を予防するためにも、難聴対策は必要不可欠です。
散歩する習慣や運動習慣を取り入れながら、しっかりと対策をしていきましょう。
また聞こえに関して不安がある方は、速やかに耳鼻咽喉科を受診し、聴力検査することをおすすめします。
-
記事投稿者

医療ライターゆし
医療機器メーカー(東証プライム市場上場)の営業職に約10年間従事。日々、多くの医師やコメディカルと関わり合いながら、ライターとして多くの医療記事を執筆している。
-
記事監修者

高島 雅之先生
『病気の状態や経過について可能な範囲で分かりやすく説明する』ことをモットーにたかしま耳鼻咽喉科で院長を務めている。■詳しいプロフィールを見る■