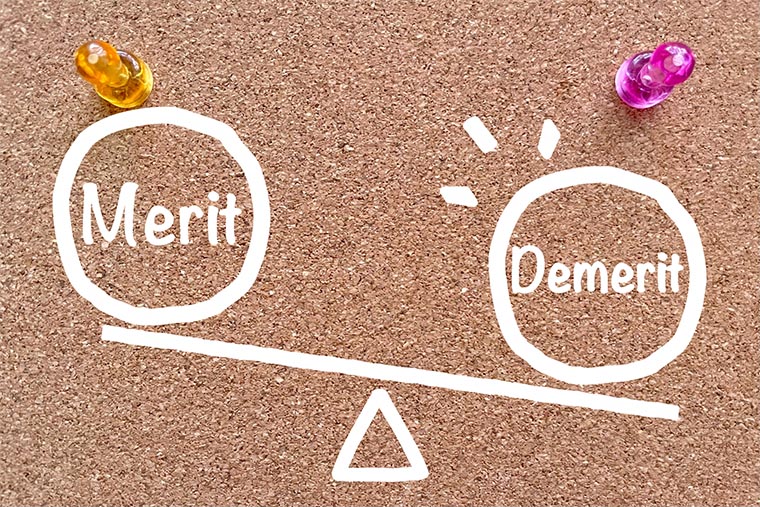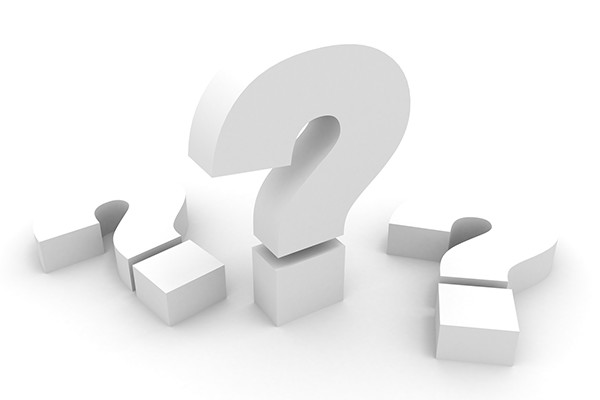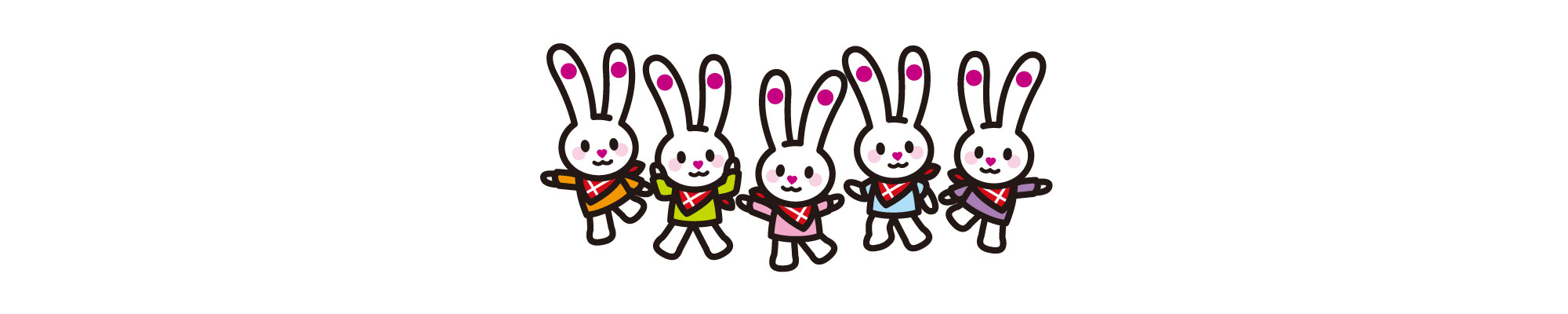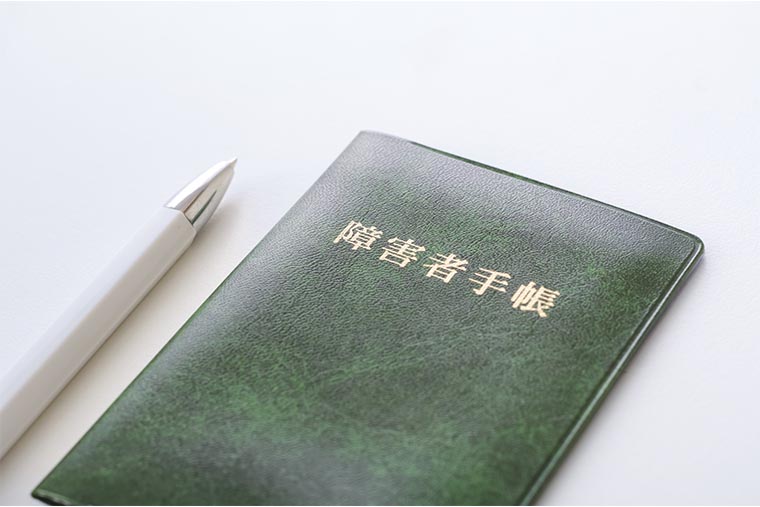
「身体障害者手帳による補聴器の補助金っていくらもらえる?」
「具体的な補助金の申請方法は?」
聴覚障害により身体障害者手帳を申請できれば、原則1割で補聴器を購入できます。ただし、補聴器の種類に応じて購入基準額が定められているため注意が必要です。本記事では身体障害者手帳による補聴器の補助金の概要をはじめとして、以下を解説します。
- 補助金の申請から交付までの7ステップ
- 補助金を利用する際の注意点
- その他の補助金などについて
身体障害者手帳の申請から補助金の交付、補聴器の受け取りまでを具体的に解説しているため、ぜひ参考にしてください。そもそも補聴器はいくらぐらいであるかを知りたい方は、「補聴器の平均的な値段はいくら?種類別、クラス別の価格相場を解説」を参照してください。
身体障害者手帳による補聴器の補助金について

補聴器の補助金の1つに補装具費支給制度があります。障害者総合支援法にもとづいて、国が実施する制度で具体的な内容は以下の通りです。
- 難聴者(聴覚障害者)の身体障害者手帳の取得者が対象となる
- 自己負担額を原則1割にできる
- 購入基準額は定められている
それぞれの詳細を解説します。
1.難聴者(聴覚障害者)の身体障害者手帳の取得者が対象となる
補装具費支給制度は、聴覚障害によって身体障害者手帳の交付を受けた方が対象になります。難聴者が障害者手帳を取得するには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 両耳の聴力レベルが70デシベル以上
- 片耳の聴力レベルが90デシベル以上、もう一方の聴力レベルが50デシベル以上
- 両耳による言葉の聞き取りの正解率(語音明瞭度)が50%以下
身体障害者手帳の交付方法については後述します。
2.自己負担額を原則1割にできる
制度を利用すれば、原則として厚生労働省によって定められている購入基準額に対して1割が自己負担額になります。自己負担額の上限は所得により以下のように設定されています。
| 市町村民税課税世帯(一般所得世帯) | 37,200円 |
|---|---|
| 市町村民税非課税世帯(低所得世帯) | 0円 |
| 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
つまり、一般所得世帯の場合、購入基準額内であれば自己負担の上限は37,200円まで。低所得世帯や生活保護世帯は自己負担が0円になります。
購入基準額を超える補聴器を購入する場合は、基準額との差額はすべて自己負担になるため注意してください。加えて、制度利用による補聴器の購入は、自由に種類を選べるわけではなく、指定医の意見書をもとに市町村が必要と認めた補聴器であることを念頭においてください。
なお、障害者またはその配偶者のどちらかが市町村民税所得割額(所得金額に応じて課税される住民税のこと)が、46万円を超える場合は対象になりません。
3.購入基準額は定められている
対象となる補聴器の購入基準額は以下のように定められています。
| 種類 | 購入基準額 |
|---|---|
| 高度難聴用ポケット型 | 44,000円 |
| 高度難聴用耳かけ型 | 46,400円 |
| 重度難聴用ポケット型 | 59,000円 |
| 重度難聴用耳かけ型 | 71,200円 |
| 耳あな型(既製品) | 92,000円 |
| 耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 |
| 骨導式ポケット型 | 74,100円 |
| 骨導式眼鏡型 | 126,900円 |
【7ステップ】障害者手帳による補聴器の補助金申請から交付まで

身体障害者手帳の申請から補助金の獲得、補聴器の受け取りまでの7ステップは以下の通りです。
- お住いの市町村の役所の福祉課窓口に相談の上、申請書類を受取る
- 指定医に診断書・意見書を作成してもらい、福祉課窓口に提出する
- 審査結果を待ち、身体障害者手帳を受け取る
- 福祉課窓口にて補助金申請の書類をもらう
- 意見書を補聴器販売店に持っていき見積書を作成してもらう
- 福祉課窓口に必要な書類を提出して審査結果を待つ
- 補聴器販売店で補聴器を受け取る
それぞれの詳細を解説します。
1.お住まいの市町村の役所の福祉課窓口に相談の上、申請書類を受取る
補装具費支給制度を利用するには、身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。まずは、お住まいの福祉課窓口に相談の上で、障害者手帳の申請に必要な書類を受け取ります。
受け取る書類は以下の通りです。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者用医師意見書(聴覚機能障害用)
市町村のホームページから、必要な書類をダウンロードできる場合がありますので、チェックしてみましょう。また、身体障害者手帳の申請は指定医に診察してもらう必要があります。事前に窓口に相談の上で指定医を紹介してもらいましょう。
2.指定医に診断書・意見書を作成してもらい、福祉課窓口に提出する
耳鼻咽喉科の指定医から診察と検査を受け、手帳交付のための意見書を作成してもらいます。なお、診断料が発生する場合があるため注意してください。
申請書類に必要事項を記載して、意見書とともにお住まいの福祉課窓口に提出します。申請書類の記入例は、市町村のホームページに掲載されていることがあるため、チェックしましょう。顔写真(縦4cm×横3cm)も忘れずに添えて提出してください。
3.審査結果を待ち、身体障害者手帳を受け取る
提出した書類は、以下のような流れで本人の手元に届きます。
- 福祉担当課によって社会福祉審議会議に提出される
- 身体障害者障害程度等級表に定められている障害に該当するか審査が行われる
- 審査により許可が下りれば、都道府県知事などが手帳を送付する
- 窓口にて障害等級が記載された身体障害者手帳が交付される
身体障害者手帳の受け取りまでの期間は、1〜2ヵ月程度必要です。障害に該当しない場合は、その理由を記載した書類が通知されます。
4.福祉課窓口にて補助金申請の書類をもらう
身体障害者手帳を持って、お住まいの福祉課窓口で補聴器の給付申請に必要な書類を受け取ります。受け取る書類は以下の通りです。
- 補装具費支給申請書
- 医学的判定意見書(補聴器用)
こちらも市町村のホームページからダウンロードできる場合があります。
5.意見書を補聴器販売店に持っていき見積書を作成してもらう
書類を用意したあとは、指定医に医学的判定意見書を作成してもらいます。こちらも診断料が発生する場合があるため注意してください。
その後、任意の補聴器販売店にて見積書を作成してもらいます。ここで注意すべき点は、障害者総合支援法に対応している販売店であるかどうかです。事前に確認しておきましょう。
6.福祉課窓口に必要な書類を提出して審査結果を待つ
次に身体障害者手帳と印鑑を持参して、お住まいの市町村の福祉課窓口にて以下の書類を提出します。
- 補装具費支給申請書
- 医学的判定意見書(補聴器用)
- 補聴器の見積書
審査が完了したら自宅に「補装具費支給決定通知書」が届きます。
7.補聴器販売店で補聴器を受け取る
「補装具費支給決定通知書」を受け取ったあとは、自己負担に必要な費用と印鑑を持参して補聴器販売店に行きます。「補装具費支給決定通知書」を販売店スタッフに提出して、自己負担額の支払いを済ませたのちに補聴器を受け取ります。
ここまでは一般的な補装具費支給制度の利用の流れです。各市町村によって必要な書類や申請の流れが異なる場合があるため、詳細は福祉課窓口で確認してください。
補聴器の購入方法の詳細を知りたい方は「【補聴器の買い方】耳鼻科受診から購入までの流れを6ステップで解説」も参考にしてください。
障害者手帳による補聴器の補助金を利用する際の注意点

障害者手帳による補聴器の補助金を利用する際の2つの注意点は以下の通りです。
- 補助対象は原則として左右どちらか1個である
- 差額自己負担が必要になる場合がある
それぞれの詳細を解説します。
1.補助対象は原則として左右どちらか1個である
補聴器の補助対象は原則として左右どちらか1個。両耳を対象にするには、職業上や教育上必要と判断された場合です。必要と判断される可能性がある一例は以下の通りです。
- 仕事上両耳装用でなければやりとりができない
- 学生であり、両耳装用でなければ講義を聞き取れない
- 幼少期から両耳装用であったため両耳の補聴器でなければならない
- 子育て上、両耳でなければ子どもの声に気づきにくい
- 視覚障害であり、両耳装用による音の情報がなければ生活ができない
補聴器を2個希望する場合は、お住まいの市町村の福祉課窓口に相談してください。
2.差額自己負担が必要になる場合がある
補装具費支給制度の対象となる補聴器は、定められた名称や機能など支給要件を満たしているものに限ります。そのため、本人が要望するデザインや素材に変更した場合に基準額を超える場合は、差額分は自己負担になります。
また、差額自己負担で購入した補聴器において修理も同様で、修理基準を超える部分の差額分は自己負担です。差額自己負担で購入を要望する場合は、事前にお住まいの福祉課窓口に相談しておきましょう。
障害者手帳の対象外の方が利用できる補聴器の補助金等について
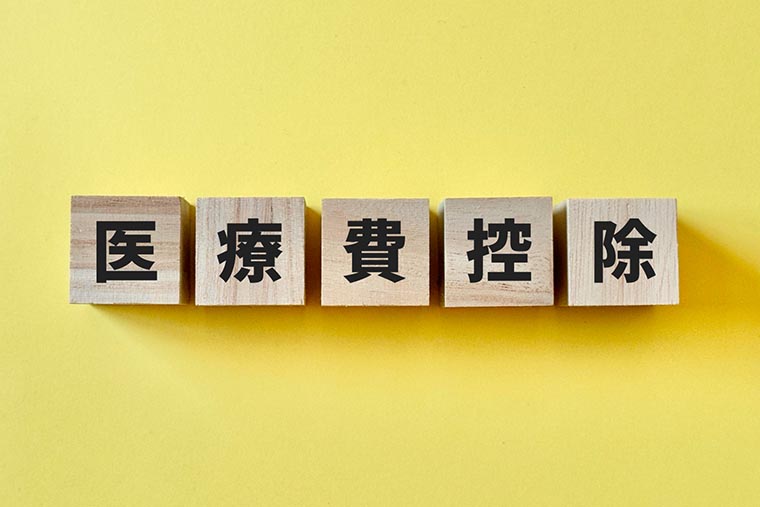
障害者手帳の対象外の方でも、以下のような制度を利用すれば補聴器の費用の負担を軽減できます。
- 医療費控除を受ける
- 各自治体の補助制度を活用する
- 片耳難聴でも利用できる補助制度がある
それぞれの詳細を解説します。
1.医療費控除を受ける
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会に認定された補聴器相談医に、補聴器が必要と診断された場合は医療費控除を受けられます。具体的な流れは以下の通りです。
- 補聴器相談医に必要な問診や検査を受ける
- 補聴器が必要と診断された場合、補聴器相談医に「補聴器適合に関する診療情報提供書」を作成してもらう
- 提供書を持って認定補聴器専門店に行き、補聴器を購入後に提供書の写しと領収書をもらう
確定申告を忘れずに実施しましょう。また、医療費控除を受けるには認定補聴器専門店、また認定補聴器技能者から補聴器を購入する必要があるため注意してください。
補聴器の医療費控除の詳細を知りたい方は「年金受給者向け|補聴器購入費の医療費控除を受けるまでの3ステップ」を参考にしてください。
2.各自治体の補助制度を活用する
地域の各自治体が独自に補聴器の補助制度を実施していることがあります。具体的な制度の名称の一例は以下の通りです。
- 高齢者補聴器購入補助金交付事業
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
自治体独自で実施している補助制度は、身体障害者手帳の対象とならない方でも、利用できる場合が多いです。自治体により要件が異なりますので、気になる方はお住まいの福祉課窓口に問い合わせてみましょう。
3.片耳難聴でも利用できる補助制度がある
地域の各自治体によって、18歳未満の子どもや65歳以上の高齢者を対象とした片耳難聴でも利用できる補助制度を実施していることがあります。
こちらも要件となる聴力レベルや所得基準、支給額は各自治体により異なります。気になる方は、お住まいの福祉課窓口に相談してみましょう。
身体障害者手帳による補聴器の補助金を有効活用しましょう

身体障害者手帳の交付を受けることができれば、補聴器を原則1割で購入可能です。ただし、対象となる補聴器は購入基準額や種類、機能などが定められているため注意が必要です。
身体障害者手帳の申請先は、お住まいの福祉課窓口です。事前に必要な書類や指定の医療機関などを確認しておきましょう。また、購入を検討している補聴器販売店が、障害者総合支援法に対応しているかどうかを確認することも大切です。耳鼻科医と連携している補聴器販売店であれば、購入や相談がスムーズになるでしょう。
「総合支援法に対応している」または「耳鼻科医との連携をしている」補聴器販売店をお探しの方は、こちらから検索してみてください。
参考
-
記事投稿者

吉沢仁(よしざわひとし)
看護専門学校を卒業後、病棟看護師として従事する。2021年からWebライターの活動を開始。医療・健康分野を専門にしており、生活習慣病や精神疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、小児疾患などさまざまな分野で執筆経験がある。医療系の総執筆数は200本以上。現在は医療系メディアでSEOライティングを中心に対応中。
-
記事監修者

若山 貴久子 先生
1914年から100年以上の実績「若山医院 眼科耳鼻咽喉科」院長。■詳しいプロフィールを見る■